「空気を読む」ってなに?コミュニケーションの謎を解いてくれたある学びと理由【体験談】
更新 2025/11/14
公開 2024/08/06
更新 2025/11/14
公開 2024/08/06

ASD(自閉スペクトラム症)があり、子どもの頃からコミュニケーションが苦手だった私。でも言葉に対して学問的な強い興味があり、この興味が私を救い、成長させてきてくれました。今回は私と「言語の勉強」との関係についてお話しします。【体験談】
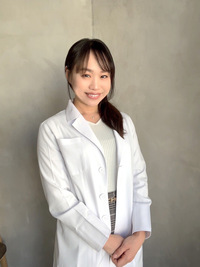
監修 : 森しほ
ゆうメンタル・スキンクリニック理事
・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋)
・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜)
・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に)
・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋)
・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜)
・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に)

