障害があると何をするにも時間がかかる…追い詰められた過去を乗り越え、自分を支える「杖」を見つけて【体験談】
更新 2025/11/14
公開 2024/09/30
更新 2025/11/14
公開 2024/09/30

こんにちは、くらげです。残暑が厳しい9月でしたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はここのところあまり体調が良くなく、かといって仕事を終わらせないことにはお賃金も入らない、というところで必死に手を動かしているところです。
障害を抱えながら仕事をするうえで困ることはいろいろあると思うのですが、おそらくその中に一つに「何をやるにしても定型発達の人より時間かかる」ということもあると思います。【体験談】
障害を抱えながら仕事をするうえで困ることはいろいろあると思うのですが、おそらくその中に一つに「何をやるにしても定型発達の人より時間かかる」ということもあると思います。【体験談】
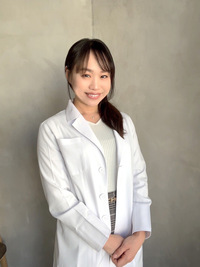
監修 : 森しほ
ゆうメンタル・スキンクリニック理事
・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋)
・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜)
・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に)
・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋)
・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜)
・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に)

