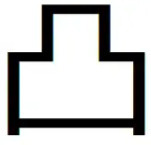ASDとADDの凸凹結婚生活、正反対だから面白い!?わが家の場合
更新 2024/11/13
公開 2024/12/02
更新 2024/11/13
公開 2024/12/02

実は私、去年結婚しました。自分は人づき合いも好きじゃないし人と一緒に生活するのもストレスを感じるので、一生結婚しないんだろうなと思ってきました。ところが、そんな私でも心が楽になれる相手が見つかり、結婚に至ったのです。今回は、「自分ルール」がはっきりし過ぎているASD(自閉スペクトラム症)の私と、細かいことは気にしないADD(注意欠如障害)の妻との結婚生活についてご紹介します。

監修 : 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授(応用行動分析学)
公認心理師/臨床心理士/自閉症スペクトラム支援士(EXPERT)
LITALICO研究所 客員研究員
公認心理師/臨床心理士/自閉症スペクトラム支援士(EXPERT)
LITALICO研究所 客員研究員