空気は読めないと自覚!だけどコミュニケーションは間違えないように。発達障害の私がしている工夫【体験談】
更新 2025/11/14
公開 2025/03/14
更新 2025/11/14
公開 2025/03/14

大阪のおばちゃんで3児の母、ゆたかちひろです。2005年生まれの長男と2010年生まれの次女には発達障害があります。子どもたちの様子を見て受診したらやっぱり私自身もADHD(注意欠如多動症)でした!今回は、コミュニケーションの工夫と、その思いについて書きたいと思います。【体験談】
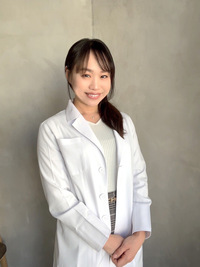
監修 : 森しほ
ゆうメンタル・スキンクリニック理事
・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋)
・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜)
・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に)
・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋)
・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜)
・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に)

