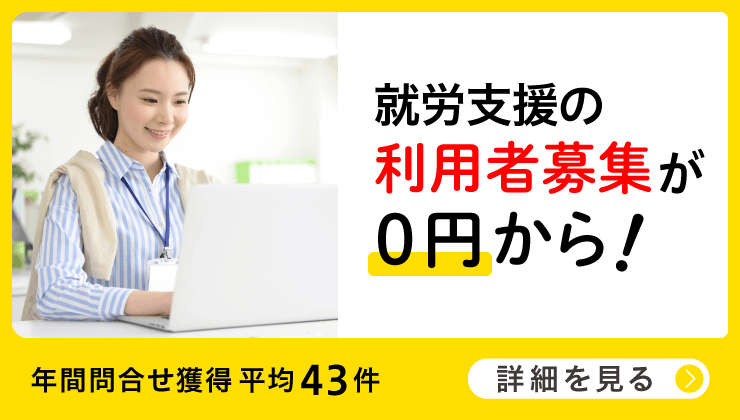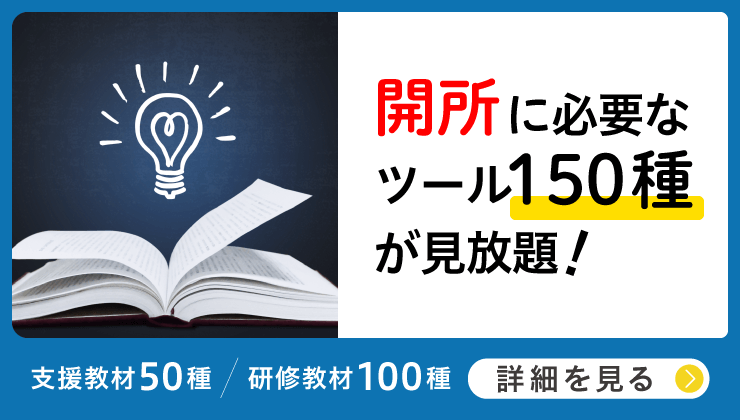サブカルビジネスセンター広島
就労継続支援B型事業所
電話でのご相談はこちら
05036280652
営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください
この事業所に問い合わせ
無料
お問い合わせ内容を教えていただけますか?
賃金・工賃について知りたい
仕事内容について知りたい
利用までの流れ・料金について知りたい
どのような施設なのか知りたい
自分でも利用できるのか知りたい
見学について知りたい
交通費や食事の補助などについて知りたい
事業所情報へ
個人的なお話~元ゲーム企画屋のゲーム談話コーナー「沙羅曼蛇」について②~
2025/04/04
(つづき)
…という訳で、ゲーム「沙羅曼蛇」のおはなし、後編です。
音響、グラフィック、バックボーン…と、かくも鮮烈だった「沙羅曼蛇」ですが、
やはり、ゲームに「映画的演出」を加えた、という点…
つまりプレイヤーが物語を形づくる、という点とそのための雰囲気づくりという点において、衝撃だった訳でもあります。
もちろん、それまでの「シューティング」ゲームというジャンルにおいて、物語は存在し、をれを彩る演出はありました。
もちろん前作「グラディウス」においても、その傾向はありました
が、それはそれまでが”ゲームのために物語”があるのであって、”物語るためのゲーム”という点において、大いなる違いが存在している訳です。
もちろん今ほど、しっかりつくりこまれている訳でもないですし、
実際には、ゲーム完成後、物語が作られた裏事情も存在してはいるのですが、結果的には…
例えば、「グラディウス」ではこあっさりしたストーリーだったことに比較し、
それまでのゲームが、敵はひとくくりの勢力だったのに対し、
バクテリアンという敵が前作「グラディウス」の激戦はいわば方面軍との戦いにすぎず、今回は「サラマンダ」という別部隊の登場であり、前作の戦いは戦略ではなく戦術的な紛争にすぎないと、実はかなり強大な敵であったという、敵キャラクターの広がりを感じさせつつ、
(この「グラディウス」や「沙羅曼蛇」が紛争レベルにすぎないという設定は、のちにスピンオフ的シミュレーションゲーム「コズミックウォーズ」(ファミコン)に活かされます)
炎の予言、
「千光年の彼方より、炎の海に棲む巨大な竜が目覚める時、狂気のフォースが迫り来て、天地は闇に飲み込まれ、やがて光は打ち砕ける」
による、神格性の盛り上げであったり
もちろん、その予言を象徴する、コアステージとして、炎(=プロミネンスが吹き上げる)ステージと、「沙羅曼蛇」から連想される、炎の龍のボスであったり、
2P同時プレイ等は、システム的には”グラディウスが2人でできたら楽しいよね”を、窮地に陥っている盟邦を、かつて危機をしりぞけた英雄が援軍に訪れ、共同戦線をもって、危機をしりぞける、という物語に落し込めている点等が、まさに”物語るためのゲーム”となっている訳です。
そして、自分が物語に参加している実感を得られるのは、何よりも当時としては、まだ珍しいサンプリング音声によるアラート音声であり、それにより、物語が始った(「Destroy Them All!」)、今から強敵(ボス)と戦う(「An intruder has penetrated our force field」)であったり…様々な音声が、物語的緊張感を高め、ゲーム映像的快楽を強化していく訳です。
(ミサイルがないだけの音声まで用意されています)
そう考えると、この「沙羅曼蛇」こそが、今では当たり前の、音声での雰囲気演出とゲームのシンクロの原点ともいえるのではないでしょうか?
そして、この「沙羅曼蛇」による物語的強化が、のちに壮大で多彩(すぎてドレがどれ?)になっていく「グラディウス」SAGAを作り上げていくのですが…
で、またしても、長文になってしまいましたので、後編のつもりではあったのですが…またのちの機会へ(つづく)
ゲームとなると話が尽きないので、申し訳ありません(笑)
■お手製CGによるビックヴァイパー<PART2>

この事業所に相談してみよう
無料